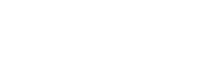
作品について
なかにし礼 作・台本 三木 稔 作曲
オペラ全3幕
イントロダクション
オペラ「静と義経」(作・台本 なかにし礼/作曲・三木稔)は、1993年鎌倉芸術館の開館記念委嘱作品として製作されました。同年、作者であるなかにし礼氏本人の演出により初演され、著名な歌手陣が多数出演し、絢爛豪華なステージとして大成功を収めました。武士が権力を握った時代を象徴する歴史上の数々の登場人物に加え、様式美も感じさせるドラマティックな音楽により、壮美なグランドオペラとして仕上げられたこの作品は、ジャパンタイムズをはじめとして各種音楽評でも絶賛されました。「日本の音楽劇で、この終幕のアリアの本当に純粋な美しさと比較できるものはかつてなく、西洋のレパートリーの中で較べられ得るアリアもごく僅か、大力作といえよう。『静と義経』はオペラのあるべき全て、すなわち、悲劇的で、華々しく、感銘的で、永遠性があり、そしてポピュラー性さえ備えた愛へのオマージュである」(ジャパンタイムズより)
昨年総監督に就任した郡愛子は初演で磯の禅師役に出演しており、日本オペラ協会創立60周年記念公演として本作品をもう一度上演したいという想いから、初演以来25年ぶりに舞台上演することとなりました。なかにし礼氏を監修に迎え、指揮には新進気鋭の女流指揮者である田中祐子を起用する一方、柔軟でありながらも手堅い演出を手掛ける馬場紀雄、振付に尾上菊紫郎、出演者には坂口裕子、沢崎恵美、中井亮一、中鉢聡をはじめとして日本オペラ協会を支えてきた数多くの歌手を配し、60年間積み重ねてきた日本オペラ上演の集大成を目指します。どうぞご期待ください!
あらすじ/見どころ・聴きどころ
【第一幕】吉野山雪の別れ
文明元年(1185年)11月
逃避行を続ける義経主従は、みちのく平泉を目指し、雪降る冬の吉野山を越えようとしていた。夜は迫る、寒さはつのる。近くの宿を借りようと思うのだが、そこは女人禁制の場所。
義経は静に、都へ帰ってくれと頼む。静は泣いてイヤだと言う。いっそ死んでしまいたい。が、静は死ねないのだ。何故。静は胎内に義経との子を身籠もっていたのだった。
ならばなおさらのこと、体をいとわねばならない。義経に説得され、財宝(おたから)と初音の鼓を形見にもらって、静は泣く泣く山を下りる決心をする。
健やかなる子供を産め、そして必ずや生きて逢おうと義経は言い、二人は〈生きてふたたび・二重唱〉を歌う。そこに弁慶、忠信、三郎、経春ら4人の家臣が歌う〈わけもなく心ひかれて・四重唱〉が重なってくる。
二人の案内人を静につけて、義経主従は雪降る吉野の白い山陰に消えていく。
残された静は、愛する人の足音の消える間もなく、二人の案内人に財宝を奪われ、その身も雪の上で犯されてしまう。
「つらくとも、苦しくとも、死にはしません。私の心の中には、あの方が住んでいるから。あの方は私の神だから。」と天にむかって泣き叫び、やがて涙かわいた静は、笠をかぶり、素足のまま、一歩二歩と雪の山路を下りはじめる。
【第二幕】鶴ヶ丘八幡宮静の舞
文治二年(1186年)4月
鶴ヶ丘八幡宮の境内は、大道芸人の芸や白拍子たちの舞い歌いに打ち興じる群衆でまさに門前市をなしている。今日、神前に舞を奉する当代一の白拍子、静御前の舞い姿を一目見ようとみな楽しみにしているのだが、突如現れた小舎人たちに群衆は、無情にも蹴散らされてしまう。
静は、歌った。愛する人の無事を祈って。静は、舞った。ふたたび逢える願いをこめて。
「賎や賎、賎のおだまきくりかえし…」〈賎のおだまき〉が、舞い終わるや、頼朝は立腹である。
「鎌倉の万歳をこそ、となえるべきところを義経などという我らの敵を恋慕う歌をうたうとはもってのほかだ。」
話はにわかに、静の胎内にある子供のことになる。政子のとりなし、義盛の諫言も功をなさず、景時の進言のままに結論が下される。
即ち、生まれた子が姫君ならば静の手に渡すが、若君ならば直ちに由比ヶ浜の海に沈める、と。
「敵の子種は残さぬ。武士の心得じゃ。悪く思うな。」と席を蹴って立ち去る頼朝。静の母、磯の禅師の悲しい祈りの歌がいつまでも尾を引いている。
【第三幕】静の死と愛のまぼろし
文治二年(1186年)7月
折しも、静母子が身を寄せている掘ノ藤次の邸の門をたたく音がする。
頼朝の使い、安達清経が生まれたばかりの赤ん坊を受け取りに来たのだ。月満ちて生まれ落ちた子は、願いもむなしく、やはり若君であった。
渡せ、渡さぬ。渡せ、渡さぬと清経と磯の禅師は、再三繰り返すが、「いずれ助からぬ身の上なら、速やかにお渡しなされ」という気丈な静の言葉に押されて、磯の禅師は涙ながらにその初孫を清経の手に渡す。清経とて木石ならぬ身、心は千々に乱れるのだが、役目にはかなわじと赤児を抱いて脱兎のごとく走り去る。それを追う磯の禅師。
放心の中にありながらも静は、死にゆくわが子のために〈静の子守唄〉を歌うのだった。
「コモに包まれ石を抱き、波を枕にねんねしな」
その歌に重なるようにして衣川で死にゆく義経主従の歌と舞いが、炎と煙の中から立ちあらわれ、そして消えていく。
〈静、都へ帰りましょう〉と母は静を慰めるかのように歌うが、静の心は一段と義経への愛を強めているのだった。
待つか、死ぬか〈二つに一つ〉私は都に帰らないと答える静。そこに世の無情を嘆く、掘ノ藤次夫婦の歌が混じり合い、哀切をきわめる四重唱となる。
文治五年(1189年)6月
墓前で、政子と娘大姫が話している。
衣川の館で義経が死んだ。裏切ったのは藤原泰衡、そう仕向けたのは頼朝。だが、本当にこの時代を動かしているのは、北条氏かもしらぬ。不気味に笑う政子。傷つく大姫。
鎌倉に届けられた義経の「首櫃」を前に、四人の男がいる。頼朝、広元、景時、義盛。
「悪は滅んだ」と頼朝がいう。「悪とは何ぞや」と義盛が訊く。
時代の流れに逆らって夢見ることが、悪であろうか。無垢な心を抱き続けて不器用に生きることが悪であろうか。だれが悪を決めるのだ。
そこへ、政子が大姫の死を告げる。
頼朝は涙を見せるが、果たしてその涙は、わが娘の死を悼んでのものなのか。わが弟九郎義経の死を嘆いてのものなのか。
頼朝は歌う。〈悪は滅んだ〉「天下のたわけもの、源頼朝、孤独地獄で狂い死にするがいい」と。政子の笑い声がいつまでも闇に谺する。
「首櫃」の前に静と磯の禅師が現れる。
「今度こそ、都へ帰りましょう」と母は嘆願するが、静の心はすでに死の淵にある。あきらめて立ち去る母の足音を背に、静は、「そこはいつも春、いつも青空、愛する人よわが君よ、いざ旅立たん、かの国へ」と、〈愛の旅立ち〉を絶唱し、われとわが胸に短剣を突き刺して息絶えるのだが…。
どこからともなく、風花の如き雪がひとひらふたひら舞ってきて―。さて、お楽しみ。
〈〉内はアリアのタイトル
※1993年公演(初演)のチラシより転載
